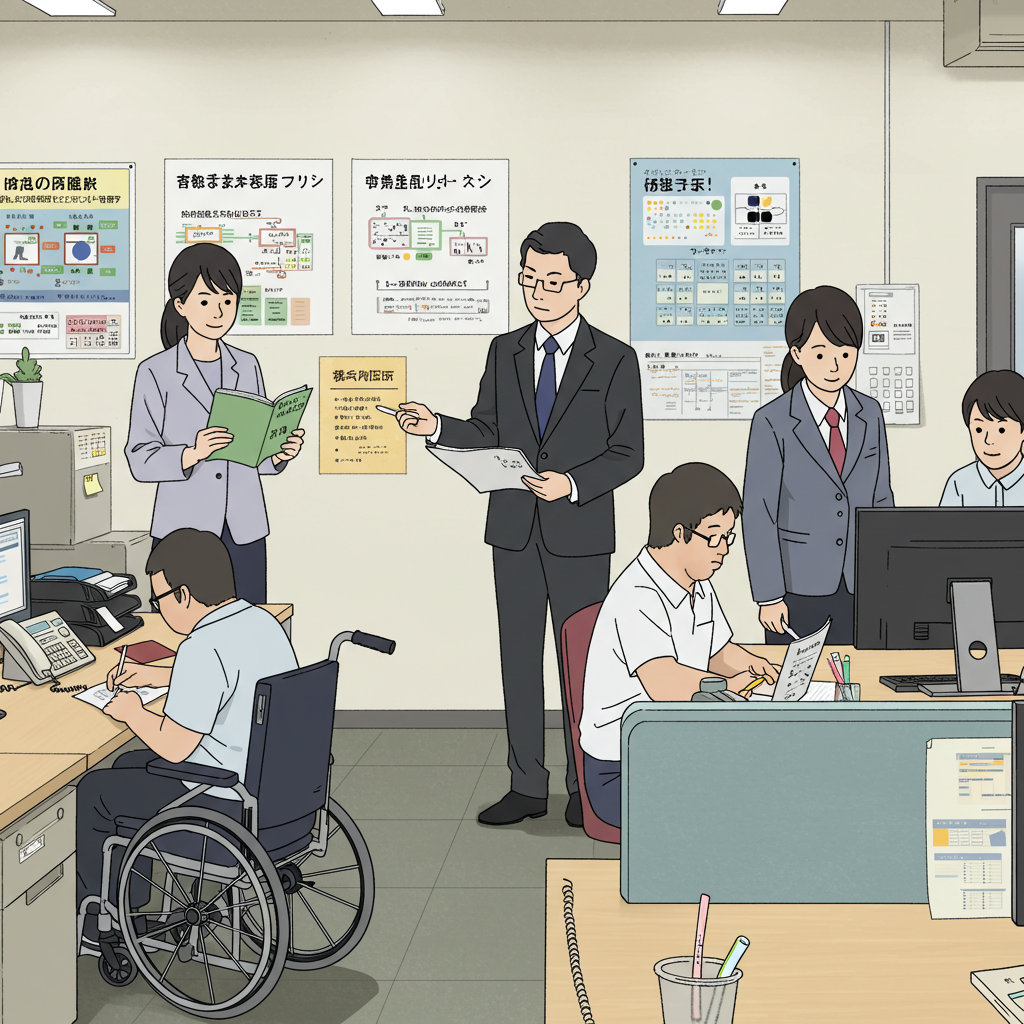🌱 障害者雇用率向上のために、今できる社内体制づくりとは
😟 「雇ったけど続かない…」そんな不安はありませんか?
障害者雇用を進める中でよくあるのが、 「雇用しても長続きしない」「受け入れ部署に戸惑いがある」 という悩みです。
これは特別なケースではなく、多くの企業が同じ壁に直面しています。
🤝 その不安に応えるのは“受け入れ体制”の見直し
雇うこと自体がゴールではなく、 「共に働き、共に育つ」 環境が本当に必要とされています。
そのために欠かせないのが、社内全体での意識合わせと準備です。
受け入れ部署への説明や研修
社内マニュアルの整備
配慮事項の共有
サポート担当者の配置
「特別扱い」ではなく「違いを前提に共に働く」という視点が、離職率低下や活躍の継続につながります。
🌈 柔軟な制度が“働きやすさ”を広げる
多様な働き方を許容できる仕組みがあれば、障がいのある方だけでなく、全従業員にとって働きやすい環境へと変わります。
⏰ 短時間勤務や時差出勤
💡 得意を活かせる職域開発
🗣️ 定期的な1on1や体調確認面談
制度は「形だけのルール」ではなく、 やさしさをカタチにする手段 です。
✨ さちなびの約束――社内連携で“続く雇用”を
実際の現場では「温度差」「支援の属人化」「評価制度の不一致」といった課題が生まれることもあります。
そこで大切なのが 人事・現場・支援担当の連携 です。
支援記録や情報の共有
定例ミーティングでのフィードバック
支援者と管理職をつなぐ橋渡し役
株式会社さちなびは、こうした仕組みを整え、 「一人ひとりに合った働き方」 を共につくることを約束します。
🚀 今日からできる小さな一歩
まずは受け入れ部署に向けた研修を検討してみる
配慮事項をリスト化して社内共有する
定期面談やフォロー体制をスケジュールに組み込む
障害者雇用は「雇ったら終わり」ではなく、信頼を築きながら続けていくもの。
社内体制の整備は、 企業の強さと多様性を育てる第一歩 です。